トーナメントの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ

トーナメントを作ることの楽しさ
トーナメント作りは無機質な作業と思われがちですが、意外な楽しさがあるものです。例えば、組み合わせ抽選会の開催です。どんな大会でも競技会でも、参加者や参加チームの代表がそれぞれ抽選箱からくじを引く時の盛り上がりは変わりありません。例えば、毎年甲子園の時期に差し掛かると、組み合わせ抽選会の様子や結果が報じられるでしょう。誰にとっても自分や自分のチームがトーナメントのどの位置に入るかは無関心ではいられないものですから、試合前の雰囲気を盛り上げる1つのイベントのように楽しいものです。もちろん、組み合わせ抽選会を行わない小規模な催しや、インターネットを通じた大会や競技会でも、組み合わせの発表時は大きく盛り上がりがあるものです。また、トーナメントを決める意外なメリットとして、大会や競技会に参加する全ての人々の士気を高めるという効果もあります。組み合わせが決まると「これから大会や競技会が始まる」という雰囲気が出てきますので、運営する側にも、参加する側にも気持ちの盛り上がりが生じるものです。こうした盛り上がりがあると、出場選手も良いプレーをしてくれるものですから、大会全体を良い物にする為にトーナメントの作成は必須と言えるでしょう。
トーナメントを作るのに用意する物
トーナメントは競技会などで勝者や順位を決める方法のことです。競技会はトーナメント方式で行われますが、トーナメントにもそのスポーツによっていくつかの種類があり、それぞれに合わせてトーナメント表を作る必要があります。 トーナメント表を作る場合には、まずはスポーツの勝敗の決まり方と、参加者または参加チームの数を調べることが重要です。トーナメント表を作るさいに必要なものとしては、紙と筆記具があれば作ることができます。 このさいに総当り戦の場合には、表計算ソフトなどを使って作ると比較的簡単に作ることができます。特に勝敗の順位を最終的に決めるものが勝率である場合には自動で計算してくれるので、便利ですしプリンターで簡単に印刷することもできます。 一方で勝ち抜き戦の場合には回戦の組み合わせと決めておく必要があります。この場合には勝ち抜きなので総当りと異なり試合数が少なくて済みますが、一度きりの試合で勝敗が決まってしまうので、やや公平性に欠けます。また下位の順位を決めるとなると試合数が増えやや仕組みが複雑になります。 このため、トーナメントでも総当り戦は一定の期間、試合を行う時間がとれるプロスポーツなどで使われ、勝ち抜き戦は短時間で勝敗を決する場合に使われています。
トーナメントの作り方の手順
トーナメント表の手作り方法としては、まずはその試合のルールを理解しておく必要があります。単純な総当り戦であれば、升目を作り、上辺と端にチームを入れることで作ることができます。端の方がチーム名で、上辺が対戦チーム名となるため、勝てば丸印を付け、負ければ黒丸印かバツ印を付けることになります。しかし、この方式の場合には同じ勝敗数になることもあり、決勝戦を行なわずに勝率などで勝敗を決める場合には、試合結果をマスに記入するケースもあります。 一方で勝ち抜き戦の場合には、予め勝ち抜きのルートを記した表を作る必要がありますが、この場合2の倍数であれば均等に作ることができますが、そうでない場合にはルートを工夫することになります。基本的には戦績から一定の回戦を経ないで上位の回戦から参加するシード方式があります。また勝ち抜き戦では決勝戦によって1位と2位が決まりますが、3位と4位を決める場合には準決勝で敗退したチーム同士による試合が必要になります。 なお、勝ち抜き戦として一般的に目にするのがイリミネーション式になりますが、このほかにもステップラダー式や、ページシステム式などがあり、それぞれのスポーツのルールや試合に掛けられる時間に合わせて作ることができます。
トーナメントの作り方のまとめ
トーナメントの手作り方法は簡単なものですので、作り方のコツを3つ覚えておけば、出場者数に関係無く適正なものを作れるでしょう。1つ目は、公正である事を心掛けることです。トーナメントはあくまで、参加者や参加チーム全体にとって平等で効率が良いシステムでなければいけません。組み合わせを操作したり、組み合わせの内容を発表前に変えてしまったりすることは、大会や競技会の結果を大きく左右する要因になります。この為、運営側は誠実にシステムを運用する責任があると言えるでしょう。2つ目は、シードを適切に配置する事です。初戦から優勝候補同士が対決したり、強力なチーム同士が対決するのもトーナメントの魅力の1つとも言えるでしょう。しかし、強い参加者や参加チームは人気も高いものですので、大会が盛り上がる中盤や後半に登場して試合や競技を行った方が面白いというのも事実です。シード権を取り入れるか取り入れないかは運営の判断に任される所ですので、大会や競技会の性質や内容に応じて判断するのが大切になります。3つ目は、組み合わせ方法の判断です。トーナメントと言えば、組み合わせ抽選会を行い、出場者や出場チームをランダムに配置するのが適切な方法でしょう。しかし、抽選には運がつきものです。仮に、強豪が別の強豪と戦って消耗しながら勝ち上がる一方で、そこそこ強いチームが弱いチームと戦って体力を温存したとすると、そこそこ強いチームが実力で劣るにも関わらず勝利する、という結果が生じるかもしれません。このように、トーナメントには最も実力の高い参加者や参加チームが勝つとは限らないという欠点があるものです。こうした欠点を補うには、運営側がトーナメントの配置を熟慮して決める措置をしなければいけません。
-

-
ライスミルクの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
ライスミルクは、少しずつ人気が出ている飲み物です。玄米を中心とした原料で作られた植物性のミルクです。多くの人が飲む牛乳や...
-
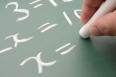
-
方程式解き方の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
方程式とは式の中に一つ以上の未知数を含んだ等式のことです。方程式は数学や物理などの専門的な研究だけでなく、さまざまな目的...
-

-
さざえご飯の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
サザエは漢字では「栄螺」と書きますが、サザエの特徴は棘のある殻にあります。これは外敵から身を守るためのものであり、大きく...
-

-
レクリエーションゲームの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レ...
レクリエーションゲームとは、その名の通りレクリエーションをする時に楽しむゲームのことです。そして、レクリエーションという...
-

-
ビーズ指輪の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
アクセサリーは大きく分けてジュエリーとカジュアルの2パターンあります。ジュエリーの場合はダイヤモンドを筆頭にパールやルビ...
-

-
おきあがりこぼしの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
おきあがりこぼしを作る理由は様々です、小学生でしたら夏休みの自由研究や工作のために作るのもいいでしょう。また、日本独特の...
-

-
梅干しきょうの料理の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
昔から梅干しにはさまざまな効能があり薬膳としても使われていました。歴史は古く平安時代の日本最古の医学書に効能が書かれてい...
-

-
アクセサリー台紙の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
ガラスビーズやパールビーズ、革紐、レースなどを使った手作りのアクセサリーは、作家のセンスとアイデアを活かして作られた世界...
-

-
割り箸ゴム鉄砲の簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
数本の割り箸と数個の輪ゴムがあれば簡単にゴム鉄砲を手作りすることが出来ます。その手作り方法は、割りばしを銃身と持ち手、ト...
-

-
メンチカツの簡単な手作り方法や作り方・DIY・レシピ
食卓のメインとなるおかずは、栄養が十分にあってボリュームもあるものが好まれます。お子様のいる家庭は特に、簡単でたべごたえ...





いかなる大会や競技会でも、多くの参加者や参加チームが出場するのであれば、トーナメントを作って試合進行をしなければいけません。集まった参加者や参加チームの中で勝敗と順位とを決める方法は様々にありますが、多くの場合はそれぞれが総当たりするのは難しいものです。参加者にも参加チームにもそれぞれに長期のスケジュール管理が必要になりますし、競技の為に多くの期間を割くのは現実的に難しいでしょう。また、資金的な理由も生じますし、競技場所も長期間同じ大会や競技会の為に使用し続ける事もできません。そこで、全ての参加者や参加チームにとって、出来るだけ素早く、かつ公平な形で順位を決められるルール作りが必要でしょう。そこで、トーナメントが役立ちます。トーナメントを作れば、全体の試合数を抑えられますし、参加者や参加チームが試合や競技を行う回数も少なくできるでしょう。このように、トーナメントには数多くの参加者や参加チームの中で順位を決める為に、平等で効率が良く、使い勝手の良いシステムであると言えるものです。トーナメントという方法はスポーツ関係の大会や競技会でよく用いられますが、参加者が対決して順位を決めるという催し事であれば、基本的にジャンルを問わず応用できるものです。